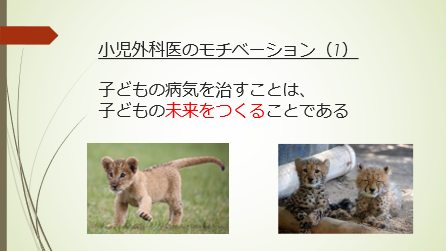短歌雑誌を読んでいるとよく具象・心象とか、写実・象徴とかリアリズム・ロマンチズ ムという字に出合う。そしてそれは相反し、相否定する概念であるらしい。何れが詩的表現の立脚的として根源的であるか、丁々発止とした論戦の見られるのも度々である。併しその論戦は何時も空転の感が免れ難いように思う。それは何れの側も自己主張のみがあって、相手の論点を自己の論点の中に包摂することが出来ないことに起因するとおもう。そこには不毛の平行があるのみである。そしてそれは写実なら写実、象徴なら象徴の出で来った本来への省察の欠除によるとおもう。相反するものがその根源性を争うということは相反するものは根源的一より出で来ったということである。斯るものに対して少し立入った考察を加えて見たいとおもう。その為に私は見るということは何かということから入ってゆきたいとおもう。
鯛は深海にあっては人間の五千倍の明らかでものを見ることが出来るといわれる。併し見るのは敵と餌だけだそうである。禿鷹は三千米の上空より地上をありありと見ることが出来るそうである。これも見るのは餌となる野ねずみだけだそうである。物があって目が見るのではない。内外相互転換的にある生命が、内外相互転換的に生きるところに見るということがあるのである。動物にとって外は食物的である。食物を摂って身体と化せんとするところに見るはたらきがあるのである。動物は行動的である。行動には力の表出が伴う、そこに外は対立するものとなる。行動的として外に対立をもつとは、空間的な生命圏を形作ることである。見るとは内と外とが生命圏に於て一としてはたらくことである。外を摂取する行動圏が生命圏である。生命圏とは餌を獲る行動範囲であり、そこは生命の形相を実現してゆく世界である。摂取の行動を起すのは欲求であり、欲求は身体の飢渇より来るのである。見るというのは外に物があって目が見るのではない。生命としての身体の欠乏の充実として見るのである。生きんとする意志が見るのである。目とは身体が行動体として、生命圏の形成に身体を切り開いて流れ出る生命の機構である。視覚の発展は生命圏の創造的発展である。
人間とは斯る生命が自覚的であるのである。人間のみにあって他の動物にないものは言語中枢であると言われる。人間は言葉をもつ動物であり、人間の身体は言葉によって動く身体である。欲求は言葉をとおした欲求であり、我々が見るとは言葉をとおした欲求に於て見るのである。言葉をとおした欲求とは、一瞬一瞬の内外相互転換を統一する、大なる生命の欲求となることである。言葉は昨日の我と明日の我を今に於て把持せしめるのである。昔語り部が個の生死を超えた歴史を語り継いだと言われる如く、過去をあらしめ、未来をあらしめるものとして、無限の生死の断絶を一つならしめるものである。無限の時が一であるとは、生命の一瞬一瞬の内外相互転換は技術的であり、経験は技術的形成として蓄積されるということである。斯る蓄積としての技術的形成が記憶である。蓄積が記憶であるとは蓄積をあらしめるものは言葉であり、言葉は蓄積として生命の初めが働くことであり、終りがはたらくことである。
人間のみにあると考えられる文化はここより来るのである。初めと終りを結ぶ生命が蓄積として今内外相互転換的に行為していることが文化的営為である。経験を蓄積するとは昨日の経験が今日働く力となるということである。昨日の失敗が今日生かされるということである。過去として消え去ったものが現在を動かしているということである。斯る意味に於て蓄積は亦創造である。私はよく用があって書道塾に行くのであるが、古代中国の手本を傍に置いて熱心に筆を動かしている。古代中国の手本で習字するということは、習うものの中に古代書家がはたらくということである。
経験の蓄積が技術的であるとは、内外相互転換が物の製作となることである。経験として過去がはたらくとは外を変革することであり、外を変革するとは、形作られた身体を内として、その秩序に外を構成することである。技術的形成として内が外となり、外が内となる内ははたらくものであり、外は物である。生命は何処迄も内外相互転換として、自覚的生命としての人間は物を作ることによって生活してゆくのである。
経験を蓄積し、物を作るということは生得的な生命圏を超えて、生命圏を拡大し多様化することである。私は其処に人間の視覚があるとおもう。鯛や禿鷹より遥に劣る視覚をもつ人間は、望遠鏡や顕微鏡をもつことによって驚異的に視野を拡大することが出来た。私達の少年の頃は肉眼で見える星は南北半球合せて六千、それが望遠鏡では十万もあると言われたものである。それが今では百億とか言われる。単に望遠鏡のみではない、見えない黒い星とか、百数十億光年とか、宇宙の塵の存在の如きは、思惟として数理の如きが視覚の内容として働いているようである。微に入っては最小単位と見られていた分子が原子の構成よりなるものであり、原子は素粒子によって構成されているという。そこも亦理論が発見よりも先行しているようである。宇宙や原子の世界は、自覚的生命の欲求の形相であり、視覚の内容である。物を作る生命が拓いて行った生命圏である。
以上いくらか私達の目というものを明かにすることが出来たとおもう。勿論短歌を作る 目は器械を介して見るのではない。直接この目で見るのである、持って生れた目で見るのである。併し単に生得的な目で見るのではない、言葉を介して見るのである。そこに私は物を介して物を見る目と同じはたらきがあるとおもう。
生命が内外相互転換的であるとは、外が内となり、内が外となることである。外の拡大は内の拡大である。外に物を知ることは内に自己を知ることである。外としての物の形相に対するものは、転換としての一瞬一瞬の喜び悲しみである。言葉を介して見るとは、言葉が物の翳を背負うことによって一瞬一瞬を凝固させ、喜び悲しみに多様なる陰翳をもたすことである。言葉に凝固したものが一瞬一瞬に溶解し、更に凝固する。そこに喜び悲しみの展開があるのである。私は斯る展開の把握が詩であり、日本的形成の把握が短歌であるとおもうものである。それは喜び悲しみとしての言葉による蓄積である。蓄積は前にも言った如く初めと終りを結ぶもの、永遠なるものの具現である。蓄積が永遠であるとは世界を作るということである。ホメロスが、ダンテが、ゲーテが、人磨が我々に呼びかけ我々に応ふるものとなることである。過去、現在、未来の一々の人々が喜び悲しみに於て応答するものとなるのである。無数の人々の心の襞が自己の心の中に陰翳を作り、当面するよろこび悲しみに形を与えてくれるのが表現である。
勿論我々の喜び悲しみの依って来るところはゲーテや人麿ではない、人と物、人と人との生きてゆく対立の矛盾である。人と物、人と人との対立そのことが世界形成であり、歴史的事件である。通常よろこび悲しみは私の中より起ると思われている。勿論私の中より起るのには違いない。併しその私は歴史的軋轢によってある私なのである。世界が自己自身を形作ってゆく一要素としての私である。そこに我々の表現衝動があるのである。我々の一挙手一投足は世界の自己具現である。世界の具現なるが故に一挙手一投足に世界を見ようとするのが表現である。
世界として物と我とが相対し、それがはたらく現在の熔鉱炉の中に投げ入れられることによって製作があるとは、それが言葉によって把握されるとき、二つの立場があるということが出来る。一つは物からの方向であり、一つは人からの方向である。一つは作られたものからであり、一つは作るものからである。製作に於て人と物、過去と未来がそこに消えるとは無にして成ることである。無にして成るとは単になくなることではない。人と物とが相互否定的に格闘することである。人と物が愈々鮮明となりつゝ転換的に一ということである。無とか消えるというのは斯る転換が世界の自己実現であり、人も物も世界の内容として対立するということである。二つの方向よりの立場が成立するとは、否定的対立として、格闘することによってあるものとして、相互転換的に対手を帯びることによって全体を把持するものとなるが故である。物よりの立場も全体の相貌を帯び、人よりの立場も全体の相貌を帯びるのである。二つの立場は相反するものとして、全体の相貌に於て激突するのである。
斯る立場から先ず具象について考えて見たいとおもう。具象とは字の如く象を具えたものであり、対象となるものである。対象とは見られたものであり、見られたものとは前に言った如く、欲求が外に象となって現われたものである。それは自覚的生命に於て物として我に対立するものである。具象とはその本質に於て物である。物は人間が製作すること によって実現するものである。人間が作るとは、内として形のなかったものが露わとなる ことである。無限に動的として形のなかった生命が、自覚的として自己自身を見たのが象であり、物である。無限に動的なる生命が自己自身を見たものとして、物は単に形として静止としてあるのではない。物は自己自身を超えて、呼声をもつものとして物である。勿論物はそれ自身に声を持たない、対象として主体としての人間に対するとき、その宿した時の深さ、技術の高さに於て見る人々に製作を呼びかけるのである。見る人々は其処に生命の大なる創造的発展を見、これも亦その創造線に参与せんと欲するのである。私はそこに写生とか、写実というのが主唱せられる論拠があるとおもう。
人と物、過去と未来が相互否定的に一であるところは、物の生れるところであり、物の生れるところが事実の世界である。自覚的形成的世界は、事実より事実へと転じてゆくのである。物の無いことは死を意味し、物を作ることは力の表出を要する。物と人が相対するとは、物は死をもって我々に迫ってくることである。我々の喜び悲しみが生死の翳を帯びるものであるとき、喜び悲しみは物が担い、物によって見られるものである。アララギの観照としての写生が、生活詠に至り着かなければならなかった所以がここにあるとおもう。
心象は具象が物に即したのに対して、言葉に即する方向である。物の象に対して、言葉は象なきものである。而して物の象は言葉によってあるのである。物は名付けられることによって自他相分ち、自他相分つことによって存在するものとなるのである。名の無き物の世界は渾沌に過ぎない。名付けられることによって自他相分ち、自他相分つことによって物があるとは、物の製作は言葉がはたらかなければならないということである。名付けられるとは一瞬一瞬の内外相互転換を超えるということである。時を超えて時を包む普遍者となるということである。時を超えて時を包むとは蓄積の内容となったということである。経験の蓄積は言葉に於て蓄積されるのである。そこに物は作られるのである。
言葉によって経験が蓄積され、経験の蓄積が物の製作であるとは、物は言葉を宿すことによって物であり、物が言葉を宿すことによって物であるとは、言葉は物を宿すことによって言葉であることである。言葉と物は互がそれによってあるものとして対立するのである。自覚的生命は斯る対立を媒介として自己自身を形成するのである。対立を媒介とするということは、自覚が深くなることは対立が鮮明となることである。物が物自身の方に内面的発展をもち、言葉が言葉自身の内面的発展をもつということである。そこに物の方向に現実の意識が生れ、言葉の方向に想像の意識が生れるのである。
想像は言葉が、内外相互転換としての情緒に結びついたものである。外としての物ではなく、内としての生命の方向に内面的発展をもったものである。私は心象をここに求めたいとおもう。よろこびかなしみは何処より来り、何処に去りゆくかを知らない。それは物の如く象をもたない、其処に言葉の自由なる飛翔がある。勿論それは物と断絶したものでない。言葉も情緒も形成作用の一面として反極に物を宿すのである。それは幻覚に過ぎない、否幻覚といえどもそれが身体より出ずるものとして物に関るのである。
情緒や言葉に宿された物は質量をもたない、或は質量をもつとしても極少にされたものである。質量をもたないということはその可塑性に於て抵抗をもたないということである。言葉はその宿す物の形象の構成に於て、空中に楼閣を築くことも可能である。言葉が情緒と結合するという意味に於て、情緒の高揚と共に拡大してゆくのである。否想像が情緒を高揚させ、情緒の高揚が想像を拡大させるのである。
自覚的生命が形成的であるとは、相反するものが何処迄も相反する方向に自己を限定してゆくことである。反極をもつことである。内外相互転換的である生命は自覚的となることによって、何処迄も内が内の方向に発展し、外は外の方向に発展するのである。そこに内外相互転換的に一であった生命は、絶対否定を媒介する一となるのである。一方向への展開は具体的な生命を失うものとして死への道を歩むのである。物はその象の固定化に於て、想像は根なき草として果てに滅亡をもつものである。死を救済し、生に転ずるのが否定的一である。想像は固定する物の象に流動を与え、生の流れに復帰を与えるものであり、物はその形の対立に於て、想像を誘発して止まざるものである。物の対立矛盾なくして想像はあり得ず、想像なくして物の新たな象はあり得ないのである。矛盾の果ての想像に理想があり、理想より見て現実があるのである。理想が大となることは、現実が愈々はたらくものとなることであり、現実が愈々はたらくことは、理想が愈々大となることである。而してこのことは理想と現実が愈々乖離することである。
勿論芸術としての、短歌表現の具象と心象は現実と理想と同一ではない。併し私は多くの点で相似をもつとおもう。現実の方向に具象があり、理想の方向に心象があるのである。具象の方向は物であり、心象の方向は想像である。異なるところは現実と理想は生活そのものにつながるのに対し、心象と具象は生活の表象の意味を有することである。現実と理想が身体の存亡に関るのに対して、具象と心象は、生命形成の真実を何れがより深く言葉に捉え得るかである。
前にも言った如く、自覚的生命の生命形成は否定を媒介する。否定を媒介するとは相互否定的に形成することである。具象が心象を否定し、心象が具象を否定するのである。象が心象を否定するとは、物が想像を実現することである。物に実現するときそこに想像はなくなる。心象が具象が否定するとは、物を想像の内容として、想像の展開をもつことである。言葉に於て形が形を生んでゆくことである。具象と心象は相互補完的である。相互補完的とは前述した如く、一方向のみでは自己の死をもつことである。他者によってあるのである。而してそれはあく迄他者によって否定され、他者を否定するものとして相互補完的である。リアリズムとロマンチズムは何処迄も闘わなけれればならないのである。対手が泣く迄言い争って相互形成をもつのである。
闘うものは勝敗がなければならない。勝敗は時が背負ったようである。本来相互補完的なるものに勝敗のあるべき筈がない。併しそれが何処迄も対立する以上、何れかが主導することによって表現があるのである。そしてその否定として次の形が生れるのである。短歌に於て万葉の具象に対して、幽玄的なものを表そうとした古今は、仏老的観念を基底にもって物を見、言葉に表そうとしたということが出来る。斯る姿勢に対して痛烈な反撃をもったのが子規以下の写生であった。そして現在短歌は写生を如何に克服しようとしているかにあると思われる。全ての形は身体を媒介するものとして、生成・成熟・老化をもつのである。形は行き詰らざるを得ないのである。行き詰るとは無限に動的な生命形成の現在を担い得ないものとなることである。そこで相反するものが世界の動的形成の底より反撥してくるのである。斯る世界形成の呼び声が、歌人をして自己の使命を感ぜしめるのである。
万葉に還れの大合唱に初まった近代短歌運動は、万葉的表現の模倣を目指すものでは決してなかった。古今集以来の作歌の根底にはたらく観念への挑戦であった。生命形成は更にその奥に直截なるものをもつことの直観であった。それは単に観念を否定するものではなくして、観念を包むものとしての現実の把握を目指すものであった。多くの人の写生論には浪漫主義を意識しての、写生の根源性の主張が読みとれる。写生の根源性とは浪漫主義を包摂するということである。現在短歌は斯る写生のより深奥に観念を見ようとするのである。そのことは近代写生のもつ理念が表現しつくされたということである。出口のない袋小路に追い込まれたということである。類型の枠より出ることが出来なくなったとい うことである。
相互否定的なるものが、相互依存的であるとは何れも根源的ではないということである。根源的なるものは、両者が争うことによって形が生れてくるということである。争うことによって生れる形は、対立するものを含むより根源的な形であるということである。万葉に対して古今は一層根源的なものを見たのである。それによって万葉的立脚点から見ることの出来ないさまざまのものを見ることが出来たのである。近代短歌は万葉に還る精神として、更に万葉にも古今にも見ることの出来ない世界を切り拓いて行った。現代短歌は写生論によって見ることの出来ない世界を創出しようとしているのである。写生論者は或はこれを否むかも知れない。併し生れ来ったものは死すべく生れ来ったのであり、現われたものは否定さるべく現れ来ったのである。表現の世界は否定されるところにこそ意義をもつのである。
具象の根源性が更に大なる心象の根源性を生み、心象の根源性がより大な具象の根源性を生むのである。そしてそれは歴史的時に映されるのである。一頃反戦を詠い、安保を詠う時局詠の如きが、新たなる短歌創造の内容の如く言われたことがある。併し対象を変えるだけで、新たな創造が出来る程安易である筈がない。それは翼讃短歌の如く言葉のみ壮にして、状況を離れれば戯画の如きが残る丈である。私達は現在の歴史的状況を詠うのではない。写生によって見ることの出来ない世界を観念より拓いてゆかなければならないのである。斯くして創り出された目が、歴史的現在の目となるのである。われわれは歴史の追尾者ではなくして、歴史を創るものである。歴史を内にもつのである。
創造的形成は無限の発展であり、多様化である。併しその一々は奪うべからざるよろこびかなしみをもつ、赤人のよろこびかなしみは、茂吉のよろこびかなしみに換えることは出来ないものである。その意味に於て一々は完結をもつのである。前のものが後のものに否定さるべくあるとは、前のものは後のものの為にあるということではない、一々は自己の奥底を見てきたのである。斯る意味に於て否定とは対話である。そこに次のものが包摂してゆく所以がある。死するもの否定さるものは呼びかける永遠の声となるのである。若し写生が否定されたとしても、その生きて見出たよろこびかなしみに於て、作歌するものに呼びかけて止まないのである。そこに歴史を超え、具象・心象を超えた短歌的表現の世界がある。具象・心象はその中に成立するのである。
長谷川利春「自己の中に自己を見るもの」