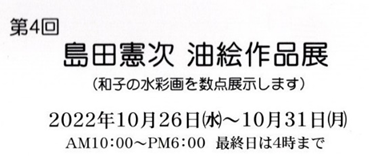先日恐ろしい映画を観てきました。
「関心領域」The Zone of Interestという、ナチスドイツが使った強制収容所の周辺地域を指す言葉ですが、ナチスに関わった人々の真の残虐さを描いたものです。映画の内容としてはアウシュビッツ収容所の所長が収容所のすぐ隣で暮らしているのですが、ごくありふれた幸福な家族の日常が淡々とつづられ、、塀を隔てた収容所での残虐さは具体的には何も出てきません。しかし、収容所の焼却炉からあがる煙、銃声、叫び声、家族が交わす何気ない会話、収容者たちから奪った毛皮のコートを自慢げに着てみせる所長夫人、川で水浴びをしていた時に流れてきた灰のためにすかさず家に帰ってシャワーを浴びる家族、貨物車で運び込まれた「積み荷」を効率よく焼却する新型「リング式焼却炉」の開発を熱心に討論する技術者たち、欲しいものは何でも手に入るアウシュビッツの自宅を離れたくない夫人に、この上ない恐怖を感じるのです。ハンナ・アーレントによる「悪の凡庸さ」つまり「命令に従っただけの凡庸な人間たち」ではなく、本映画に登場するのは積極的に「劣等人種」を殺戮し自分のより良い生活を確保するために搾取を意識的或いは無意識に行う普通の一般人から成り立つ「支配民族」であることが強調されます。

上記のハンナ・アーレントは何故ドイツでナチスのような全体主義が台頭したかについて、詳しく分析されています。つまり「客観的な敵」を規定することが「全体主義」の本質であるとし「客観的な敵は自然や歴史の法則によって体制側の政策のみによって規定され、これらは効果的に人間の自由を奪う」としています。一旦「客観的な敵」が規定されると「望ましからぬもの」「生きる資格の無いもの」という新しい概念、グループが出来上がり、「客観的な敵」に属さない「大多数の人々」はこれに賛同し、また「同調圧力」が加わり「大虐殺」に至ったとしています。「大多数の人々」がこのような「均一性」を自覚することが最も根源的な問題と思われ、多様性を受け入れることが重要と思われますが、ナチスドイツだけでなく現在も続いている多くの紛争は、異なる民族、宗教の違いにより生じ「支配民族」たることを目的としていることによるものと思われ残念ながら解決は難しいように思われます。
(2024.6.29)